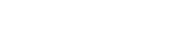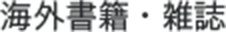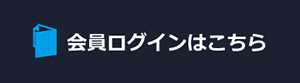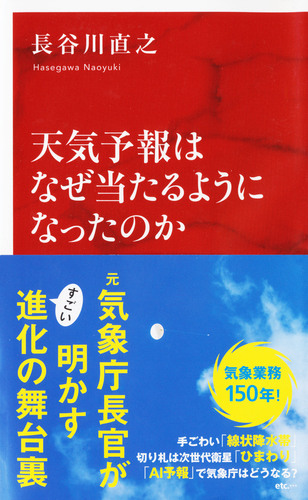
複雑すぎる「気象の方程式」をいかに計算するか
『天気予報はなぜ当たるようになったのか』
長谷川 直之 著
|
集英社インターナショナル(インターナショナル新書)
| 256p
| 1,012円(税込)
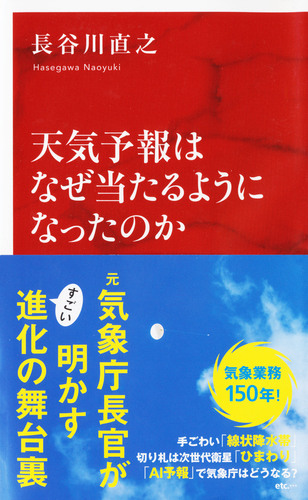
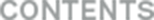
1.天気予報はなぜ当たるのか
2.気象情報で命を守れ
3.防災気象情報の舞台裏
4.線状降水帯予測への挑戦
5.地球温暖化をどう伝えるのか
6.天気に国境はない
7.気象データは誰のものか
8.これからの天気予報

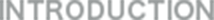
かつては外れることも珍しくなかった天気予報が、近年「よく当たる」と感じる人は多いのではないか。実際、気象庁が発表する天気予報の精度は向上している。背景には、コンピューターの性能向上や衛星データの出現などがあるようだ。では、具体的に、天気予報はどうやって作られているのだろうか。

本書は、元気象庁長官の著者が、自らの経験を踏まえて天気予報の作り方や最新事情を解説している。気象は、一般的な物理法則で説明がつくものである一方、天気予報を導き出すための「方程式」は複雑で、「数値予報モデル」と呼ばれるコンピュータープログラムを用いて無理やり計算しているという。また、天気は地球全体の影響を受けて変化するため国際協力が進んでおり、すべての国が統一された方法で気象の観測を行い、すべての国で情報交換して使えるような仕組みが整えられている。直近は、機械学習によって気象予測を行う「AI予報」なども始まっているようだ。著者は一般財団法人気象業務支援センター理事長。1983年に気象庁に入庁。2021年1月から23年1月まで第27代気象庁長官を務めた。