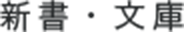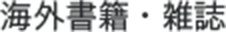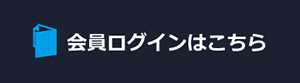なぜ「問う力」を鍛えるのに読書が有効なのか
『問いの編集力』
思考の「はじまり」を探究する
安藤 昭子 著
|
ディスカヴァー・トゥエンティワン
| 264p
| 2,090円(税込)

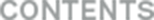
はじめに なぜ「問い」を「問う」のか
1.「問い」の土壌をほぐす
2.「問い」のタネを集める
3.「問い」を発芽させる
4.「問い」が結像する
5.「内発する問い」が世界を動かす
おわりに 「問う人」として

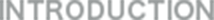
多様化・複雑化する現代では、既存の問題を解決するより、顕在化していない問題を発見することの重要性が言われている。ビジネスや教育などの場で「答え」よりも「問い」をつくる力が重視され始めているが、そもそも問いはどうやって生まれるのか。「問いが生まれやすい」思考や手続きはあるのだろうか。

本書では、問いを生み出す思考のプロセスを4段階に分けながら、自分の内側から湧き出る「内発する問い」とそれが発生するメカニズムについて、情報編集の仕組みを探究する「編集工学」のエッセンスを交えて語っている。「問う」とは身の回りにあるさまざまな情報を「編集」することであり、一つの情報を多面的に捉える柔軟な見方を身につけることで、問うべき観点や好奇心が引き出されていくという。さらに、書物を選んだり読んだりすることが、未知への想像力を刺激し、「読む」「問う」双方の力を鍛えるとも説く。著者の安藤昭子氏は編集工学研究所代表取締役社長。企業の人材・組織開発や理念・ヴィジョン設計、教育プログラム開発や図書空間プロデュースなど、多領域にわたる課題解決や価値創造の方法を開発・支援している。