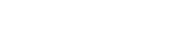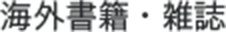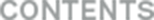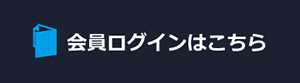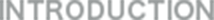
代表的な日本固有の文化的価値観に「侘び寂び(wabi sabi)」がある。茶道(茶の湯)や和歌・俳句などに表れ、禅など日本の精神文化が世界に広まる中で注目されるようになった。
世界共通で誰でも持ちうる美意識にもなりつつある「侘び寂び」ゆえに、ビジネス教養として理解しておく必要があるのではないか。

本書では、グローバルな概念としても定着している「侘び寂び」の概念をテーマに、日本史上の、主に茶道との関わりに言及しながら、心理学の知見も踏まえて「どう理解すべきか」を解説している。
対で用いられることが多い「侘び」と「寂び」だが、両者には違いがあり、前者は人の表情や所作、作品の外見などに表れたもの、後者は内面に潜む、より抽象度の高い概念。裏切りが日常で、明日をも知れぬ覚悟で生きていた戦国時代の武将は「寂び」に似た価値観を持っていたと考えられるという。
著者は社会心理学者で、東洋英和女学院大学人間科学部教授、NLPU認定マスタートレーナー。茶名「宗心」として、裏千家淡交会巡回講師、裏千家学園茶道専門学校理事を務める。